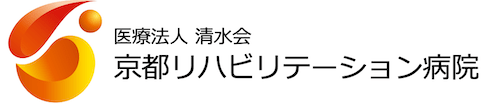ごあいさつ
看護部では、急性期の治療から、さらに機能を回復し以前に近い状態で退院ができるように
患者さん、家族さんの視点に立ち、退院までの看護援助に努めております。
また入院中、日々のリハビリテーションで自分の能力を高められたことが、日常生活に
繋げられるように、体調管理・安全管理を行いながら援助しています。
また、回復期リハビリテーション病棟協会認定研修を修了した看護師も在籍しており、
専門領域における看護の質向上を目指しております。
特に自宅に戻られる患者さんから自立ニーズの高い排泄自立に関するケア、患者数が多い
脳血管疾患の高次脳機能障害の方へのケア、家に帰られた後も安定して歩けるように「足」
そのもののフットケアに力を入れております。
私たちは患者さま、家族さまとともに「日常生活に向けて一歩ずつ進める」看護を提供します。
看護部 紹介
回復期における看護として強化している取り組み
フットケア支援チーム
「歩いて帰ろう」

足の指の変形や爪の異常、タコ、魚の目が原因で起こる疼痛や乾癬は歩行困難や転倒に直結し、
日常生活動作や生活の質の低下を招くと言われています。私たちフットケア支援チームは、
入院時に足病変の有無と足病変の種類をスクリーニングシートを用いて評価した個別ケアを
行い、セラピストと情報を共有して靴の選定なども行なったり、多職種で取り組んでいます。
摂食支援チーム
「食べられるように・・・」

摂食支援チームでは多職種が連携し、患者さまの個別性に基づいた話し合いを行い、
計画を策定、その実施・評価を行なっています。また、定期的な勉強会も開催されています。
入院時は、口腔ケアの指導、(患者さまに合った様々な口腔ケア物品の取り揃え)、画像評価(VEVF)による嚥下機能評価に基づいた個別性のあるプランニングを行っております。
排泄支援チーム
「自分の力でトイレへ行こう」
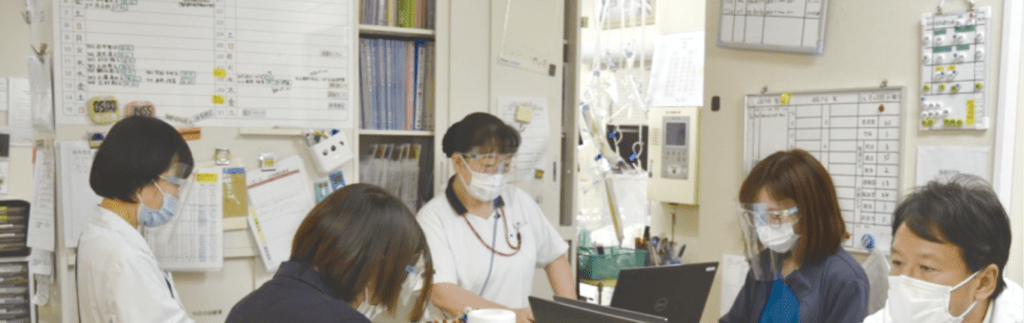
私たちは、下部尿路機能障害を評価し、多職種協働で排尿の自立に向けた包括的排尿ケアの計画
を策定、その実施・評価を行なっています。
排尿自立支援カンファレンスを行い、看護師による排尿誘導や生活指導、セラピストによる
排尿に関する動作訓練、医師による薬物療法などを話し合い、トイレでの気持ち良い排泄を
目指しています。
看護部から患者さまへ
患者さま、家族さまとの信頼関係を築きながら、入院生活が有意義に過ごせるように、患者さまそれぞれに合ったリハビリテーション看護を提供し、日々のリハビリテーションが皆さまの日常生活動作の自立に繋がるように支援致します。