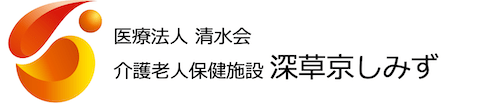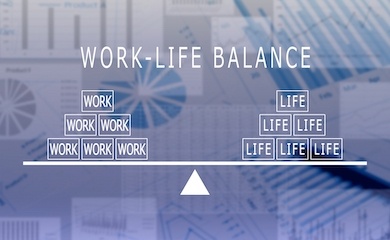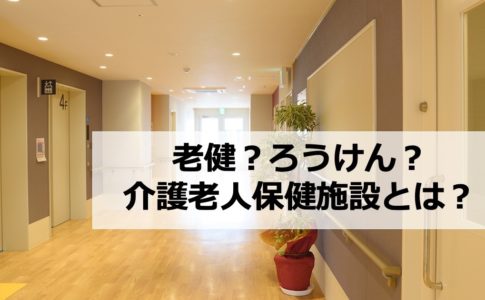超強化型老健について今回はお話しさせていただきます。
介護老人保健施設の歴史
介護老人保健施設(以下:老健)の歴史は、介護保険法の開始(平成12年)以前の昭和の時代までさかのぼります。
そして昭和60年代、高齢者の社会的な課題として、入院後のリハビリテーションを
十分に行い、かつ、介護のケアを受けるような環境が整っておらず、長期入院を
余儀なくされることが問題でした。
そこで、旧厚生省(現厚労省)は、医療と介護それぞれの機能を持つ施設の創設を目的に、
昭和62年に全国7都市で初めて現在の老健のモデルとなる施設を作りました。
その後、医療機関と在宅をつなぐ「中間施設」としてモデル事業を実践し、昭和63年に
本格的な介護老人保健施設の実施運用が始まりました。
地域包括ケアシステムと介護老人保健施設
時代は平成となり介護保険制度(平成12年)の施行、そして、令和へと元号が変わり、
その間も高齢者や、その介護者を取り巻く環境は刻々と変わってきました。
今現在、国民の4人に1人は65歳以上となり、厚労省の推計によると、2040年問題ともいわれ
るこの先の将来は、医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれると言われています。
さらに、少子高齢化による社会保障の仕組みの変化、医療の進歩による平均寿命の伸び、独居高齢者の増加など、様々な介護課題に直面している時代と言えます。
そこで、国はこれまでの社会保障のあり方や医療・介護サービスの提供について、地域単位で
必要なケア体制を整え、住まい・医療・介護・予防や生活支援が一体的に提供される、
地域包括ケアシステムの構築を提唱しました。
(参考:厚労省「地域包括ケアシステムについて」
超強化型老健 深草京しみずの役割
地域包括ケアシステムが機能するということは、すなわち、高齢者の住み方(どこで生活する
か)、看取り(どこで死を迎えるか)、地域との連携、認知症ケア-サポート、要介護状態への
予防的取り組みといった様々な介護課題に対して、地域の医療、介護資源、行政のサポート、
地域住民同士の関わりが活発になることでもあります。
深草京しみずは、医師をはじめ、看護、介護、リハビリ、栄養、相談員、ケアマネジャー、
それぞれの専門職によるケアを提供し、高齢者のリハビリテーション、生活機能の向上、
生活支援を行っております。
同時に、日々在宅介護を担われる介護者家族の皆さまに介護休息の機会を確保
し、加えて必要な介護指導、アドバイスをさせて頂き、介護者の皆さまのサポートを全力で行い
たいと考えています。
「住み慣れた地域で最期まで」を目標に、1人1人の高齢者の方々が望まれる生活が実現
出来るように、職員一丸となってケアをさせて頂きたいと思います。
在宅復帰支援機能
平成24年の介護報酬改定では、老健施設の在宅復帰・在宅支援の能力を高めていく目的で、
老健施設の呼称が、その支援の質に応じて、新たに「在宅強化型」、「加算型」、「従来型」
と呼ばれるようになりました。
平成30年には、老健施設の在宅復帰支援機能がさらに強化され、在宅復帰・在宅支援の機能
のみならず、以下の項目に関する充実度を老健機能の目安とすることとなりました。
老健機能の目安基準
- 在宅復帰率在宅復帰支援者の人数、割合。復帰率30%以上、50%以上の2段階で評価。
- ベッド回転率毎月の入所‐退所の人数。積極的に入所者の受け入れを行っているかの指標。
- 訪問指導利用者の自宅に訪問し、必要な介護指導、リハビリテーションや生活環境の助言を
行っている。 - リハビリ体制充実したリハビリテーション体制、セラピスト(理学療法士等)が規定の人数
以上配置されている。 - 支援相談体制利用者、家族様の各種相談や支援についての窓口となる相談員の人員が規定
以上配置されている。 - 重度者要件要介護4~5の利用者の方が施設をご利用されている人数。全体の35%以上、
50%以上の2段階で評価。 - 医療看護体制胃ろうなどの経菅栄養者の受け入れ、吸引等の処置が必要な方の受け入れを
積極的に行っている。
その他、地域貢献活動などの社会資源として、活動を行ってるなどの指標があります。
支援内容は指数化され、指数の合計(=在宅支援機能)がもっとも高い施設は、
在宅超強化型(超強化型老健)と呼ばれています。
老健の介護報酬改定による類型の変更
在宅復帰を中心とする様々なケアを評価される時代に変わってきている
- 従来型
- 加算型
- 強化型
- その他型
- 基本型
- 加算型
- 強化型
- 超強化型
超強化型老健 深草京しみずの在宅復帰率
深草京しみずは、平成28年の開設以来、職員一丸で質の高いケアを目指し取り組んできました。その結果、令和2年1月より、最上位の基準である「在宅超強化型」(超強化型老健)を取得しました。
過去の在宅復帰率については以下の通りです。