今回は注意障害について書いてみます
さて、そもそも注意障害ってなんだ?
注意障害とは?
脳卒中などの病気やケガなどによって脳に損傷が起きることで高度な脳の働きが障害された状態が「高次脳機能障害」です。
また加齢によっても注意力は低下しやすくなります。高次脳機能障害は、外見上は大きな問題なく生活できているように見えるので
気付きにくいという特徴があり、「見えない障害」とも言われています。
今回は高次脳機能障害の中でも注意障害について取り上げさせて頂きました。注意障害は大きく下記の4つに分類され、それぞれの対応策も簡単にご紹介いたします。
①選択性注意の低下:【見つけられる力】
多くの情報から今必要な情報だけを選ぶ機能が低下し、隣の人が気になったり、色々な ものに反応しやすくなる。
対応策➡仕切りをしたり、周りの刺激を取り除き、気が散る原因を取り除く。
②持続性注意の低下:【続けられる力】
注意力や集中力を持続させて1つのことを続ける機能が低下し、疲れやすかったり、途中で投げ出しやすくなる。
対応策➡こまめに休憩がとれるように配慮する
③転導性注意の低下:【変えられる力】
1つのことに注意を向けているときに、他の別のことに気付いて注意を切り替えることが難しく、課題を変えることが苦手になったり、直前にやっていたことと混乱したりする。
対応策➡注意の転換が必要ない環境を作る(何かをしている時は電話を切るなど)
④分配性注意の低下:【同時に何かを行う力】
いくつかのことに対し、同時に注意を向けながら行動するという能力が低下する。(電話をしながらメモが取れない、料理の途中で他のことをして料理が焦げてしまったなど)
対応策➡なるべく1つずつやるようにする。
ちょこっと!リハビリ知識







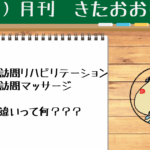
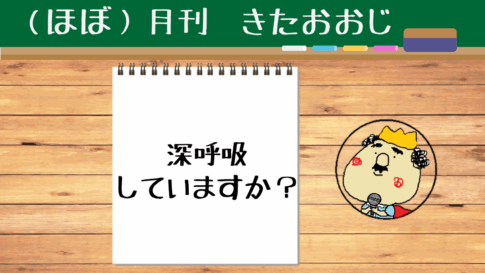
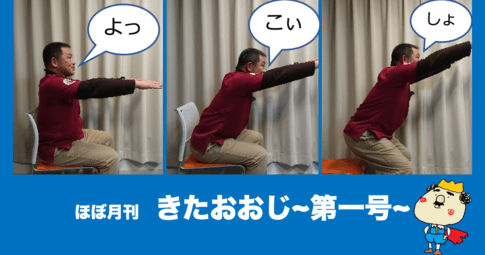
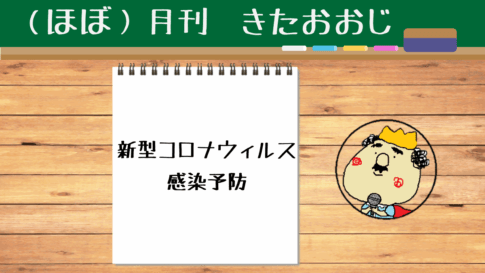
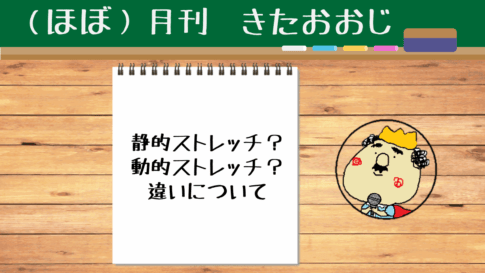
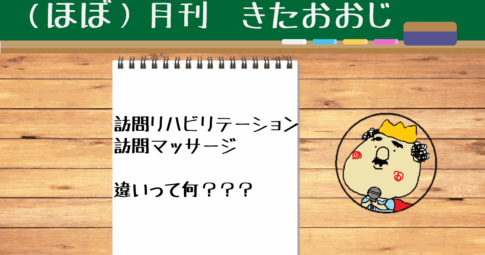
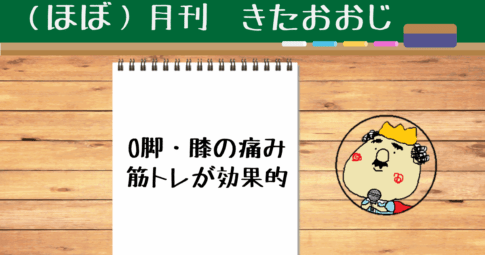
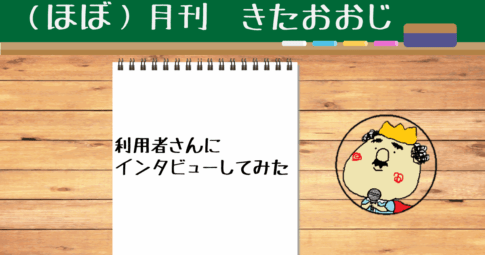
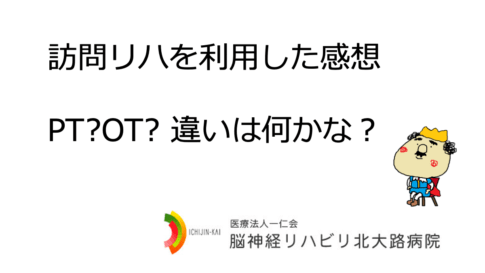
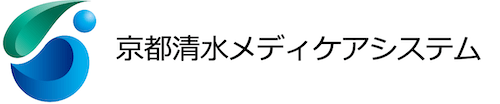

注意障害を活かしてアプローチ!!
目に映るものに注意が向きやすい人(視覚的注意が向きやすい人)には、注意が向きやすい高さや色(赤や黄色など)を考えてポスターや張り紙を有効に使う。
聞こえる音に対して注意が向きやすい人(聴覚的注意が向きやすい人)には、アラームや音声を有効的な手段に使ったり、その人の注意の向きやすさを活かしてアプローチに取り入れることもあります。
注意障害の症状は個人によって様々です。
また、自分の注意力が低下しているということに自覚がない人も多くいらっしゃいます。
注意障害の改善には『自分の注意力が落ちていることに気付くこと』が大切といわれています。