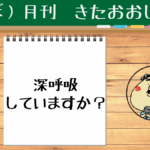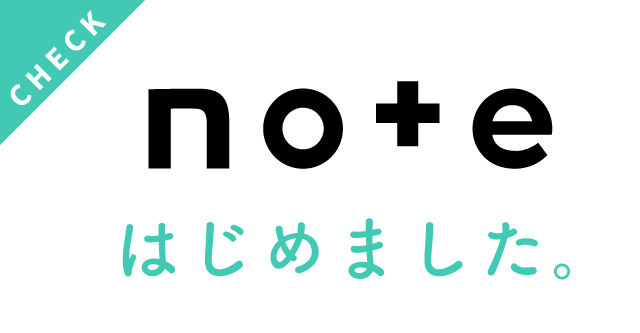「なんとなく寂しい」認知症外来でときにそんな声を聞きます。
仕事も退職し、子どもも独立。友人とも会えなくなり、今までしていた趣味もできなくなった。では、今の自分というのは何が喜びなのだろうか、人生に喜びと言えるものはあるのだろうか。そういう疑いが起こってきます。今まで意味があると思ってきたものに信頼を置けなくなってしまった、確かなものなど何もない、という疑いです。
では私たちはその「確かなもの」をどこに見ているのでしょうか。それはいのちの価値をどこに見ているか、ということもできます。それは患者さんの「寂しさ」が教えてくれます。家族には慌ただしい生活の中で、「できない」ことを責められる。病院では知能検査で評価される。そんなふうにいのちの価値を「能力」で量られ、私自身を見てもらえない、私の悲しみを聞いてくれない、だから「寂しい」のではないでしょうか。
そういう量ることのできるいのちではなく、量ることのできない私自身、悲しみや苦しみを抱えながら生きる私のいのち全体を敬う眼差しがない。だから呼吸をしたり心臓が動いたりという「生命」としては生きていても、”いのち”が生きられなくなる。そういうことがあるのではないででしょうか。
私は寺に生まれたというご縁で、大学で仏教を学ぶことになりましたが、そこで教えていただいたのは、自分のものさしで決めた、プラスとマイナスのいのちの価値を越えた、いのち全体を敬う眼差しがあるということでした。それを仏の智慧と呼び、その智慧によって、いかに自分が、自分のものさしによって勝手にいのちの価値を決めつけ、自分自身のいのちを傷つけ、他者のいのちを敬うことができなくなっているかということを知らされました。
世間の価値観では、マイナスをプラスにすることばかりを考えがちですが、マイナスの中に、つまり苦しみや悲しみの中に、人間として生きることの大事な意味を確かめるということがあってこそ、やがて死んでいくという同じ悲しみを生きる者として、共にいのちを敬いあうことのできる場所が開かれるのではないでしょうか。
<四季報2020年4月号掲載>
脳神経内科 岸上 仁